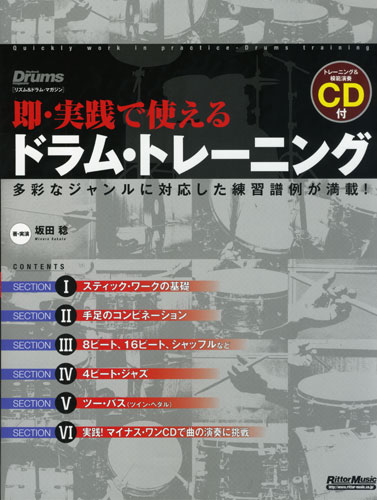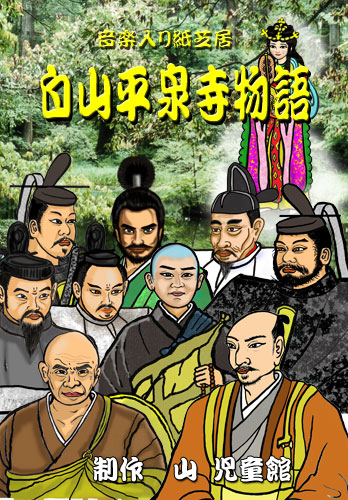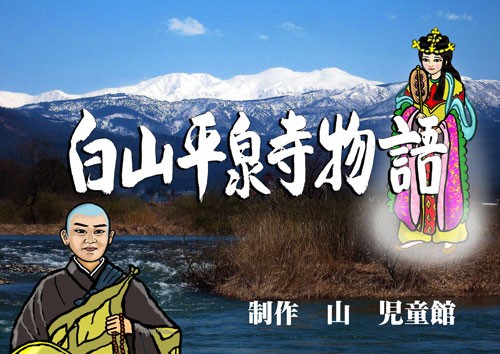伝えたいこと
来週の29日に「勝山城友の会」の総会の後、話をしてほしいと依頼された。打ち合わせの際、「私は造語が好きです。例えば、“我が家あってふるさとなし”とか……。」と話したところ、それが話のタイトルになってしまった。
でも、私の「今、伝えたいこと」と、そんなに外れてはいないと思っている。今日の午後、話の中身を考えた。先ず、唱歌『ふるさと』の歌を聴いてもらってから話を始めたいと思っている。
ふるさと
1.兎追ひし かの山
小鮒(こぶな)釣りし かの川
夢は今も めぐりて
忘れがたき 故郷(ふるさと)
2.如何(いか)にいます 父母
恙(つつが)なしや 友がき
雨に風に つけても
思ひ出(い)づる 故郷
3.志(こころざし)を はたして
いつの日にか 帰らん
山は靑き 故郷
水は淸き 故郷 (恙:病気や災難を意味する)
私流の解釈で、今なぜ“ふるさと”がなくなったと私が考えているかを考えてみたい。先ずは、唱歌「ふるさと」の歌詞を参考にしながら私見を述べたい。
1番では、自分が遊んだり関わりを持った山や川などの自然について述べている。漫然とそれらが“ある”のではなく、自分が関わりを持っていた地域の自然や神社や公園などがあり、そこにはいろいろな思い出があると言うことだろう。
今の子供達には、関わりを持った自然や場所がどれだけあるだろうか。私の場合は、村の背後にある大師山(泰澄大師ゆかりの山)は、中学生時代に子供だけでキャンプをした思い出の山である。
栗を拾い、アケビを取り、山菜を採った山でもあり、何度も足を運んだ山であるのだ。麓では、まっすぐな木をのこぎりで切り、それを剣にしてチャンバラごっこをした山でもある。薪を取りに何度も足を運んだ山でもあるのだ。
村の神社にも多くの思い出がある。毎年夏休みには、ラジオ体操をし、ソフトボールをし、箱を並べて勉強をした思い出がある。
祭りには、太鼓を叩き、秋祭りなどには、民謡やフォークダンスを踊った思い出の場所でもある。また、子供を背負う帯をまわしにして相撲を取った場所でもある。
村の中も思い出の場所である。村中を舞台に大がかりな“鬼ごっこ”や“缶蹴り”、“ポコペン”、“瓦倒し”など様々な遊びを行ってきた。防火用水は、泳ぎの場であ離、魚を釣った場所でもあった。
季節季節に、どこにどんな果実が実るのかを知っていて、拾いに出かけたところでもある。柿、梅、桑の実、銀杏等を拾いに回ったところでもあるのだ。
村の付近を流れる川は魚を釣った場所であり、九頭竜川も水泳や魚を捕まえた思い出の詰まったところである。自分が関わった思い出の場所なのだ。
2番目では、父母や友達が出てくる。父母は、凛としていた。怖い存在でもあったが、よき理解者でもあった。また、遊んだ仲間も地域には多かった。また、いろんな遊びや道具の使い方を教わった先輩達がいる。将棋などを教わった大人や先輩がいる。
私がギターに興味を持ったのも、村の先輩達が弾いているのを見て興味を持ったことがきっかけだった。このようにいろんな人たちと多くの関わりを持った自分の地域は、ここを離れても思い出すであろう。
3番では、いつかは帰りたいと思う。それだけ、自分の居場所のあった地域と言うことになるのだろう。それが“ふるさと”と言うことではないか。
今の子供達は、自宅と学校または習い事をする場所を行き来していることが多い・大人も、職場と自宅を行き来するだけのことが多い。家がどこかへ移っても、そんなに困らないのではないか。
昔に比べると、地域とも、周囲の人とも、関わることが非常に少なくなっている。これでは、“我が家あってふるさとなし”と言われても仕方がないであろう。
それなら、どうすればよいのか、ここらか持論を展開したいと思う。理屈だけではなく、自分のやってきたことをまじえて話すことができればと思っている。
(日記:午前中、里芋の土寄せ。マルチを半分外して於いて、溝を作りそこに少し蔬菜肥料を入れ、鍬で里芋の根本に土を寄せた。非常に熱く、汗はだらだらと出て、体重も減ったようだった。その後、シャワーをして休憩し、今度は事務所横の家庭菜園を耕した。そして、ニンニクを収穫した後に黒瓜を植えるための場所を作った。とにかく今日は熱かった。午後は、パソコンで「我が家あってふるさとなし」の原稿作りをした。午後7時半から和太鼓の練習。今日も事務所の机を叩いてイメージトレーニング。新しいポジションの者だけ太鼓を使って腕の振りを練習。)