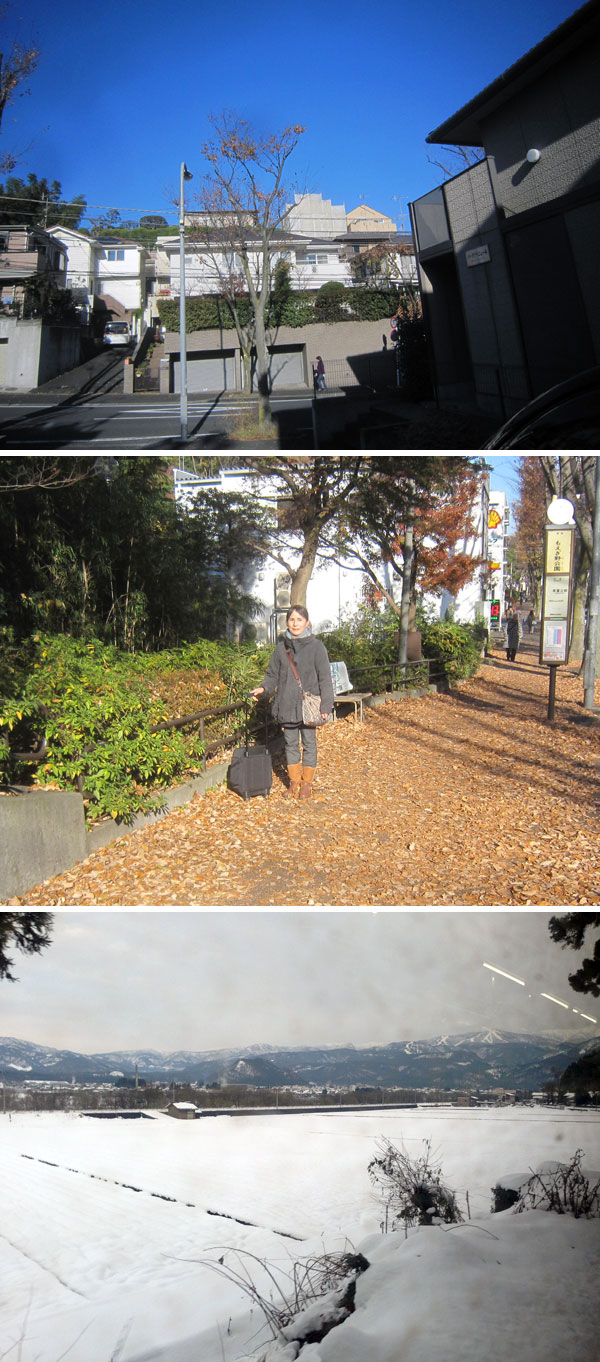楽しくなきゃあ
半日は,全く自分のために、そして半日は、家族のためにと決めている。選挙の後、私は事務所で数学。参考書作り。遅々として進まない。しかし、毎日パワーを信じて、取り組んでいる場すこしは前へ進むだろうと思っている。
目休めに、時々ギターを弾いている。エフェクターを使い、アンプを通すと、おとに変化が出て生ギターとはまた違う響きがする。50年前に弾いたアドリブを思い出しながら、楽しんでいる。
数学も、数楽でなければと思っている。解くことが楽しい、第三者にわかってもらうことが楽しい、この二つが数学の楽しさだろうか。どちらも、考えなければできない。
一方、ギターの方だが、弾いているうちに歌詞とメロディーが浮かんできた。歌作りでは、無理矢理歌詞やメロディーを考える場合と、ギターなどを弾いているときに自然に浮かんでくる場合がある。
今日は、珍しいことだった。家へ帰ってから、久々にパソコンの前で歌づくりを始めた。自分の言いたいことを歌詞にしてみただけだ。やはり、自分の心の中から滲み出てくるものでなければ人に訴えるものはできないと思う。どんな歌になるか楽しみだ。
(日記 午前9時頃選挙に行き、その後、事務所で数学(楽)。時々ギターを弾きながらの作業だった。事務所前の駐車場に融雪装置を設置した。と言っても、川から水中ポンプで水を揚げ、ホースの先につけた穴開きっパイプで散水するだけだが。午後は、自宅の整理・整頓・清掃。年末大掃除というところか。夕食後は、選挙速報を見る。)