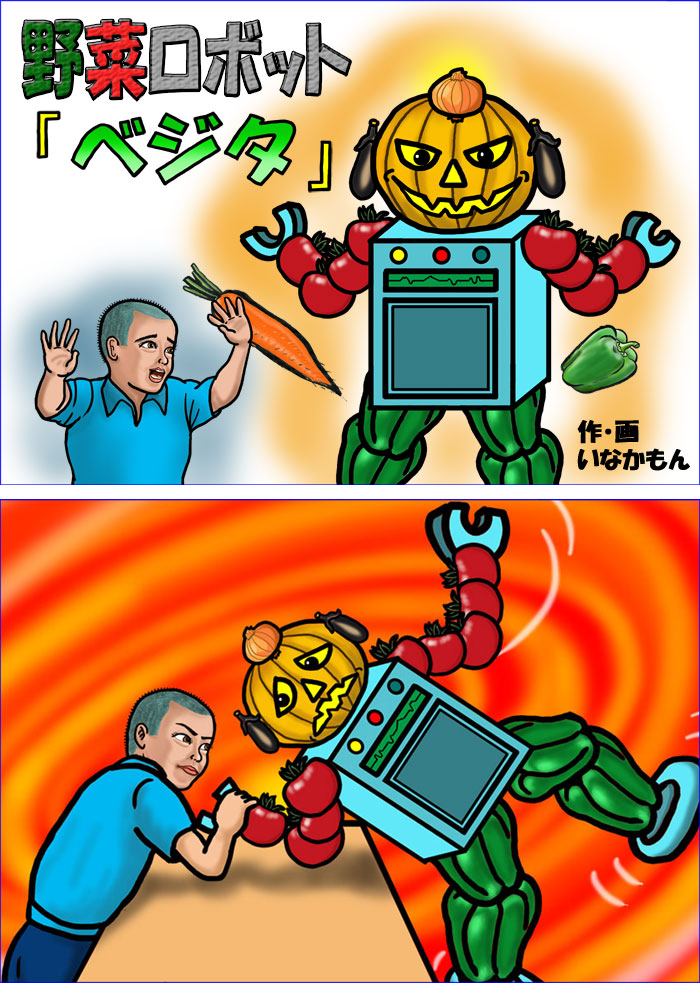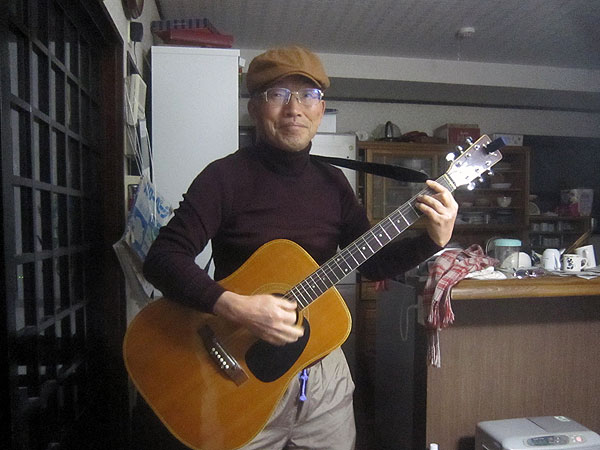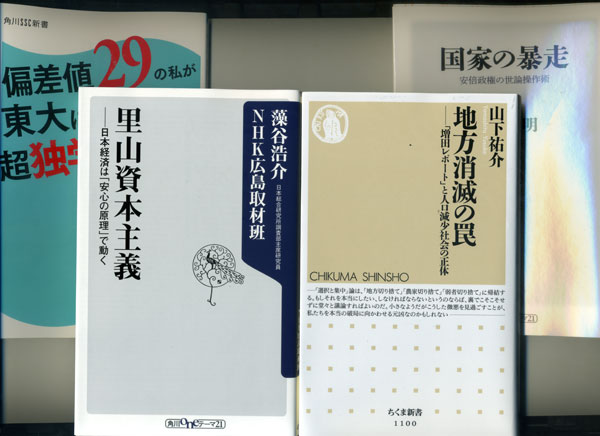風邪だけは引くまい
今週末に次女の結婚式がある。私達夫婦は、風邪だけは引くまいと思っていたが、数日前に今年三度目の風邪を引いた。毎日、何とか週末までには直したいと思っていたが、直ったような治らないような状態で東京へ出発することになった。
礼服などは、昨日宅急便でホテルへ送ったので、荷物はそんなになかった。今回は、リュックを担いで行くと決めた。午前8時過ぎの「えち鉄」で東京へ向かった。勝山はそんなによい天気ではなかったが、東京は快晴であった。
早速、新宿西口のヨドバシカメラ店へ寄ってカメラを見ていると、「カメラをお選びですか」と若い店員が寄ってきた。的は二つに絞ってあったので、それらの違いを店員に聞いた。
問題は、今日買ったときに付く点数を今日使えるかということであったが、ウェブ店に申し込み、手続きをすれば使えるととのことであった。キャノンのEOSM2を買うことにした。
その後、身体を休めるために、ホテルへ向かった。二人とも道中ずっとマスクをつけていたが、ようやく取り外すことができた。少しずつ結婚式が近づいているのだという気持ちがわいてきた。今回の結婚式をもって3人の子どもの結婚式は全て終わることになる。最後の結婚式だから滞りなく終わってほしいという気持ちで一杯だ。
(日記 午前8時にタクシーで自宅を出発。「えち鉄」「北陸線」「新幹線」を乗り継いで東京へ。新宿駅近くの「ヨドバシカメラ」でキャノンの「EOSm2」を買った。そして、駅近くのホテルで宿泊。)