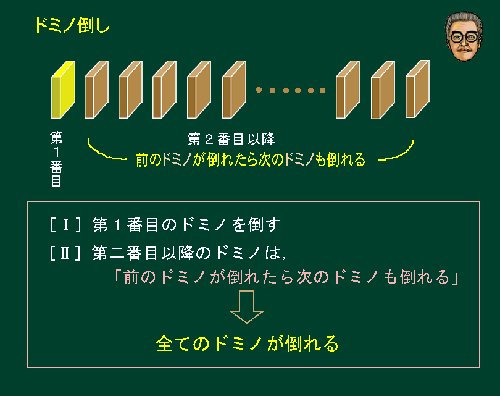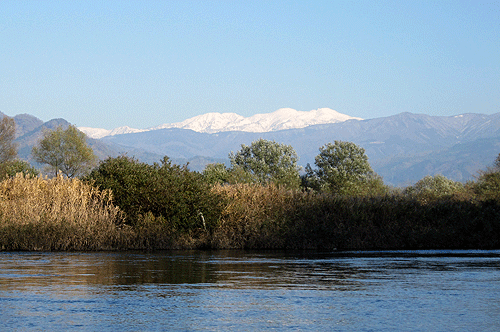モノがない分“想像力が育った時代”
今の世の中は、私たち60歳前後の世代の子供時代に比べると比較できないくらい豊かになっている。豊かになったと言っても、それは“モノ”に関してだけであって、豊かになったとは必ずしも思えない。
我々の子供時代は、モノに関しては極端に少なく、今とは比べものにならないほど質素な生活であったように思う。しかし、それが貧しかったとは思わなかった。
ざっと考えただけでも、肉などは年に二回しか食べることはなかった。(一度は農作業の最終日、臼すりの日、もう一日は大晦日であった。)
また、車などはもちろんなく、一家に一台、自転車がルだけであった。(そもそも子供自転車など存在もしなかった。)そのために、子供達は、俺これ創意工夫をして大人の自転車にチャレンジしたものだ。
私に地区では、自転車の乗り方には“さんまた”、“中また”、“大また”と三段階があった。自転車の車体の三角部分に右足を入れて乗るのが“さんまた”、自転車の座席に座らず、車体の辛抱に座って乗るのが“中また”であり、これは身体が小さくてペダルに足が届かないための苦肉の策であった。
ようやく足が届いて自転車に乗ったのが、“大また”であった。しかしながら、いつでも自転車を使えたのではない。父親が会社から帰ってきた後のわずかな時間にしか自転車を使えなかった。
自転車を借りるためには、その代償として自転車を磨くことを求められた。自転車のスポークの一本一本をぼろ布で磨いたものだ。テレビなどもなかったし、いわゆるゲーム機などは存在もしなかった。
モノがない分、創意工夫をしてあらゆることにチャレンジしたものだ。これは、遊びだけではなく、技術の習得についても同様であった。地区の仲間とは様々な行事を通じて遊んだりしたものだ。
モノがない分、豊かな経験があったと思っている。しかし、その頃育った者は親になって、子供達に苦労をさせまいと一生懸命働いた。
“豊かな時代”になったとは言うけれど
数十年前と比べると、物質的には比較にならないほど豊かになった。しかし、その結果、どうなったであろうか。人間が劣化しているのではないだろうか。
近年、子供に対する異常な犯罪が頻発している。一見普通に見える(実は普通ではない)者が突如として凶悪事件を起こすのである。その度にその対策がは検討される。
しかし、子どもたちの安全を守ることが非常に困難な時代になってきている。それは、異常な犯罪者だけではなく、普通の大人が、突然異常な犯罪を起こす可能性がどんどん増えている。
子供は年をとれば、大きくなれば大人になるのではない。子供を持てば親になるのでもない。大人になったり、親になるには、経験したり、習得しなければならないものがたくさんあるように思う。
子供を大人にする仕組みとして大きな役割を果たしてきた「地域社会」や「家庭」が崩壊している。子供のまま大きくなった「オトナ」がどんどん増えている。
個人も、集団も、国家も不信感を持ったまま歩みを続けている。日本海周辺は今や危険な地域になってきている。その中で、今さえよければと言う刹那的なオトナが増えている。
今まで社会は、ある種の信頼関係の上に成り立っていた。しかし、いつ何が起こるかわからない時代になりつつある。特に異常な犯罪が増加しているように思えてならない。世の中が二極化してますますそのスピードが速まっているように思う。
今後ますます防犯カメラは普及するだろう。“人を見たら犯罪者と思え”と教えなければならない世の中になりつつある。さぞかし住みにくいだろう。不信感に満ちて寒々として世の中では、更に次の犯罪者を産み出しそうである。
今の世の中が“子どもたちにとってはどうか?”ということを大人達は真剣に考え、子どもたちの成長の妨げになるモノを大人達がこれ以上作り出さない、示さないことが大切ではなかろうか。
私たち大人が、“モノを作ること”と“人をつくる(育てる)こと”を混同しているうちは、人と人とが信頼し合える世の中をつくることは困難であろう。
今の世の中のシステムや大人達の言動、そして自由の横行が、次の犯罪を産み出す予備軍を育てることにならないよう私たちは、勇気を持って変えるべきところは変え、守るべきところは守り、規制すべきところは規制すべきではなかろうか。
自由とは、責任を伴って初めて意味を為し、権利とは義務を伴って初めて論じることが可能になることを自覚すべきであろう。つまるところ、子供の問題は全て大人の問題であると私は思っている。
(日記:午前中、雪囲いの最終コースである植木の雪囲いをした。午後も作業を継続した。太陽が出ていてとても気持ちがよかった。2時頃から6時頃まで事務所で数学のホームページ作り。夜は8月頃の『龍馬伝』を見る。薩長同盟成立の頃の話であった。今なら、信じられない大事件だ。と言うよりも犯罪として扱われるだろう。龍馬達はまさに生きていると感じて行動していたのであろう。)