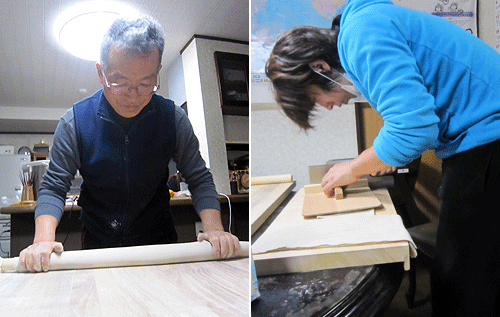雪と戯れる
正月には仕事で帰省できなかった息子が家族を連れてやってきた。休みを取って4泊5日でやってきたからには、こちらは正月のつもりで対応することにした。
今日は雪になるとの予報でったが実際にはとてもよい天気になった。孫達はソリとスキー、息子はスノーボード、私はスキーと片瀬オリジナルのソリを持って雁ヶ原スキー場へ出かけた。
最初は、孫と一緒にソリを楽しんだ。息子達家族も2台のソリを連結したりしながら童心に返ってそれを楽しんだようだ。途中で休息をとり、孫のスキーにも付き合った。
途中で息子はスノーボードを、私はスキーを楽しんだ。久々のスキーであった。脚力が弱っているなあと痛感した。20歳代、30歳代とは筋力などはずいぶん弱ったようだ。
今から鍛えるわけにもいかないが、弱まるスピードをゆっくりしたいものだ。日々、柔軟体操や筋力アップのためにせめて週1回はプールへも行きたい。
帰り際に、子ども達が最も夢中になったのは、ソリやスキーではなく、スキー場の端に積まれた雪山から滑り下りることだった。もう一回、もう一回と何回も雪の山に上り下りした。
考えてみれば、子どもが夢中になることは、必ずしも大人が考えるようなものではないかもしれない。既成のおもちゃを子ども達が喜ぶだろうと思っても、子ども達はすぐ飽きてしまって空き缶は空き箱などに夢中になることが多いものだ。
我が家の孫達も、動かない(危ないので電源を切ってある)ウオーキングマシーンを電車に見立てて遊んでいる。いくつもメーターが付いているからだ。
とにかく、子ども達は一日中、ソリや雪山遊日などに夢中になって、勝山の冬を楽しんだようだ。私自身も、孫達のおかげで、スキー場へ足を運んだために、いろんな人に会うことができたし、スキーをすることもできた。
親子でソバ打ち競演!?
正月の年越しソバのつもりでソバを打つことを決めた。息子が半分、私が半分、最初から最後まで責任を持ってソバを打った。息子の嫁と家内はおろしを作ったり、天ぷらをあげたり、している。
みんな喜んでくれたので、ソバの打ち甲斐があった。どうも、水加減などは、何度も打っているうちにわかることかもしれない。素人の私には、マニュアル通りではうまくいかない。
やはり、色々やっているうちに、マスターできることかもしれない。習うより慣れろだ。そば粉などがあれば、私は何とかソバを打てるなあと思った。これからも、機会あるごとに、ソバを打ってみたい。
(日記:午前中、雁ヶ原へ出かける。午前中、宗教行事で道場へお参りしていた家内も、昼食時に合流。午後も、スキー、ソリ、スノーボードなどを息子や孫達と楽しむ。夕方、息子とソバ打ち。孫達も喜んで食べてくれた。夜、息子に、パソコンの設定などを頼む。充実した1日であった。)