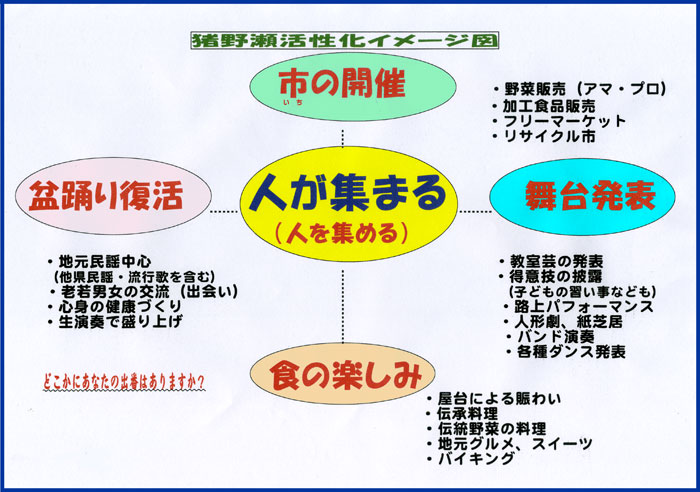階段作りパート1
白山を開いた泰澄大師ゆかりの大師山が我が片瀬区の背後にある。この大師山周辺は、猪野瀬地区や旧勝山町が所有している山だ。現在は越前大仏もかなり所有しているが。
最近では、この山へ出向くことは、春の山菜採りぐらいだろうか。それと時々行われるたいまつ登山などのイベントぐらいだろうか。

階段の材料を担いで現場へ出発。(大師山山頂にて)
しかし、子どもの頃はそうではなかった。正に生活に密着した山だった。特に、家庭での重要な燃料としての薪はこの山でしか手に入れることができなかった。
栗拾いや山菜採り、そして小鳥を捕まえるためにもよく山へ行ったが、なんと言っても、薪取りが最も多かった。夏の暑い日に、村の共有林のある大師山の裏側まで出かけて両親が作った薪を担いで自宅まで運んだのだ。
この作業は子どもにとっては重労働だった。しかし、プロパンガスが出てきてからは薪の需要は激減した。正に燃料革命だ。そして、今また電気による生活に変わってしまった。
おかげで大師山へ出かけるのは、レクレーションだけになってしまった。私にとっては、山菜採りも、レクレーションの一つだ。そんな中で、大師山へ登る人、大師山を経由して三ツ頭山や報恩寺山へ登る人が増えた。

セイバやスコップで溝を作り、そこへ階段を設置して固定するための杭をカケヤで打ち込めば一段完成。
登山道はもはや生活の道から、レクレーションの道へ変わってしまったようだ。付近に山を所有している人は、杉の下草刈りぐらいには出かけるかも知れないが。
この大師山登山道の整備をここ数年、『猪野瀬地区まちづくり推進協議会』を行っている。今日はその一環として登山道にプラスティックの階段を取り付けるためにまちづくり関係の者が山へ登った。
来る日曜日には、登山の目印とするために「何合目」と書かれた石柱を立てることになっている。登山口からと山頂から石柱を背中に担いで運び、登山道脇に設置するのだ。
当日は、階段作りも行うが、今日は下見を兼ねて20段の階段を設置した。参加者は7人、午前7時に村の集会所へ集まり、山頂まで資材を運び、担いで下山しながら所定の場所に階段を設置した。
一番勾配が急で滑りやすい場所に階段を設置した。来る8月13日の『大師山たいまつ登山』には整備が終わり、気持ちよく山登りができるのではなかろうか。
(日記 午前7時に片瀬集会所前へ集合。軽トラに分乗して大師山山頂へ。7合目と8合目の間の急な場所に階段を設置した。帰宅後シャワーをして遅羽公民館へ。『遅羽さわらび会(食生活改善推進員)』の親子料理教室で食後のアトラクションとして家内と紙芝居をするためだ。恐竜を題材にした紙芝居をした。午後は、『コミュニティー助成事業』の事務処理。午後7時より和太鼓の練習。最後の詰めを行った。まだ、あちこち直すとよい場所が出てくる。メンバーと知恵を寄せ合い手直しをしながら練習をした。後10日で本番だ。悔いのないゆに練習したい。そう言えば、今日の福井新聞に出場チームの写真が掲載された。気分がだんだん高まってくる。)