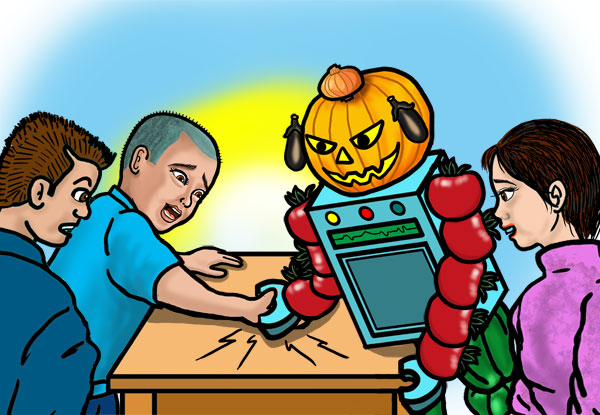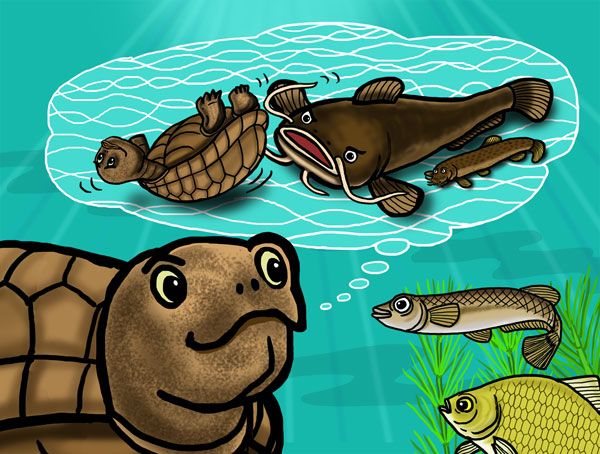お風呂物語
子どもの頃、風呂を沸かすのは私の役割だった。手伝いではない。私が風呂を沸かさなければ誰も風呂には入れない。当時風呂を沸かすのは大仕事だった。
パソコンの中に、『昭和の子ども』と題して私の子供時代のことをいろいろ書いた詩(と私は表散る思っている)がある。
風呂
風呂を沸かすは 子の仕事
手押しポンプで 水汲んで
バケツに入れて 水運び
胸まで差し上げ 風呂ヘジャー
小学生には 重労働
五回・十回 くーたくた
おまけに釜から 水漏れだ
火が消え煙が もーくもく
目痛い涙が ポーロポロ
薪持った手で 涙拭きゃ
顔中炭で インディアン
笑い事では 済まされぬ
外へ突進 二度三度
新鮮空気で 元気つけ
またまた煙の 中へ行く
風呂が沸いたら お隣へ
「湯、入んに来とくんねんしぇー」
当然ふれ事 子の仕事
同じ湯再度 沸かした日
「古湯ですけど、入んに来とくねんしぇー」
またまた近所を 一回り
この頃は五右衛門風呂で水がもれ大変だった。その後、風呂はタイル張りになり、電気温水器になって風呂を沸かす仕事はなくなった。
そして、風呂はステンレスになり、今はボタン一つで好きな温度で風呂を沸かすことができる。この半世紀でずいぶん便利になった。
薪を必要としなくなっただけでもありがたかったが、さらに進んでボタン一つになったのだ。正に“隔世の感”である。便利さの陰で何かが失われていくのだろう。
(日記 午前中は、紙芝居の追加の絵描き。今週の土曜日に、猪野瀬公民館で行われる高齢者サロンで創作紙芝居『親鸞聖人物語』を演ずるためだ。一度平泉寺公民館で演じたものをマイナーチェンジするために絵を描き加えた。もう2、3は描き加えたい。午後は、家庭菜園の片付け作業。トマトの支柱を片付けた。トマトはほとんどが枯れていたが、2本だけ実を付けていたので残しておくことにした。畑のイチジクは、毎日10個ずつ実を付ける。いくらイチジク好きでも食べきれない。今日も、隣人にあげた。それで
も自宅にはたくさんのイチジクがあり、食べきれないので家内がイチジクジャムを作った。パンにのせてもヨーグルトに入れても美味しい。今日は畑でキウイを120個収穫した。まだまだある。キウイはこのままでは食べられない。リンゴなどと一緒に追熟しなければならない。冬の美味しいフルーツだ。イチジクもキウイも畑仕事のプレゼントだと思っている。自然の恵みに感謝。夜は再び、紙芝居の絵描き。)