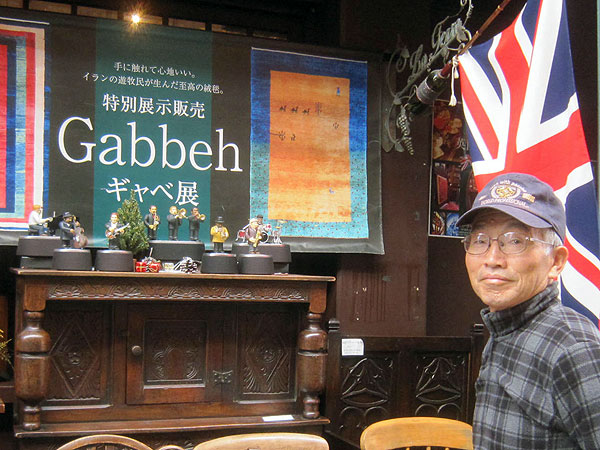秀吉の開いた長浜
彦根城と長浜城を見学して“地方創生は武将に学べ”と思った。特に、長浜城博物館で「秀吉のまちづくり」のビデオを見てその感を強くした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
羽柴秀吉が初めて一国一城の主になった今浜が、長浜に改められ、1574年に城が築かれたという。秀吉は、小谷城下の商人を統合して「楽市楽座」の制度で城下町を形成するとともに、町衆の保護・自立のためにに「町屋敷年貢免除」の朱印状を与え、まちの繁栄をもたらしたのだ。
1615年に、長浜は彦根藩の一部となり、廃城となったが、「町屋敷年貢免除」は江戸時代を通して維持され、長浜は水運の要に位置するまち、浜ちりめんやビロード、火や等のまちとして繁栄を続けたのだという。
『曳山会館』を見学して、このような経済力を背景にまちの文化も栄えたことを知った。『長浜曳山まつり』もその源をたどると秀吉に行き着くという。日本三大山車祭の一つで、国の重要無形民俗文化財に指定されている。子どもから大人までが一体となって祭りに取り組む様子をビデオで見て改めて感心した。これらの伝統は今も長浜に息づいているのだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
昔の殿様のまちづくりには学ぶことが多いと感心した。湖北の歴史のたびでまちづくりに対するいろんなヒントがあると思った。金沢を作った前田利家、財政再建を成し遂げた米沢藩の上杉鷹山などにも学ぶことが多いように思う。
『大河ドラマ』と言うと、とかく買った負けたという戦と権力を描く場面が多いが、まちづくりにもっと光を当てるべきではなかろうか。
(日記 朝起きるなり、高速を走り、彦根ICで下り、彦根城を見学。その後、湖畔をドライブして「黒かべ」へ。車を駅前に止めてマップ片手に、町中散策。よくもこんなにたくさんの店が並んでいるものだと感心する。今日は11月22日で“いい夫婦の日”だ。「記念にネックレスを買ったら」と家内にすすめる。長浜ラーメンを食べて長浜城を見学。特に、長浜城博物館で見たビデオ「秀吉のまちづくり」には感心した。その後、木之
本IC出高速に乗り、帰宅。夜は、猪野瀬公民館で行われた松井県議の「県政報告会」に出て、ひげの隊長“佐藤正久氏”の集団的自衛権などについての講演を聴く。)