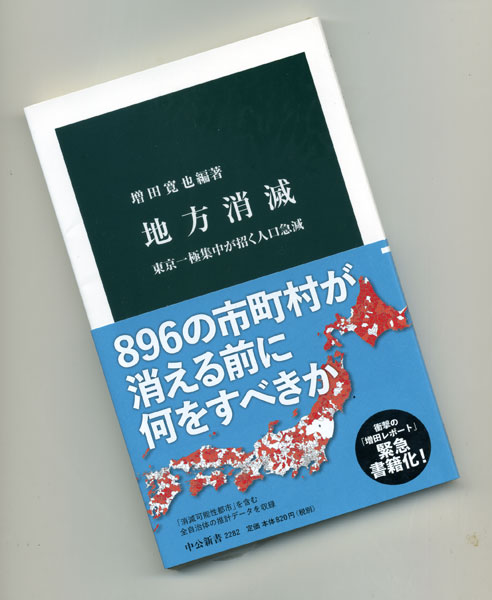席取りに並ぶなんて
息子の孫の発表会を見るために幼稚園へ向かった。福井の孫の時もそうであったが、横浜の孫たちの発表会に保護者は並ばなければならないのだ。まるで、スターのショウを見るために並ぶようなものだ。
各年代5クラスずつあるそうだ。そのため、発表会は、全年齢を3班に分けて行うそうだ。保護者は、少しでも見やすい席を確保するために、幼稚園の外で並ぶことになった。快晴だったのでよかったが、雨でも降ったら大変だ。
午前9時になると、園長先生の挨拶が始まり、年少、年中、年長の園児の歌や踊りの発表があった。息子の次女は、年長組なので、オペレッタ『ジャックと豆の木』を演じた。
芝居や歌があり、セリフの合間や歌の伴奏はステージを見ながら担任教諭がピアノで伴奏するのだ。自分の子供が演ずる時には、ステージの真ん前に用意されている絨毯席で見ることができる仕組みだ。
一つ、プログラムが進むたびに、保護者の入れ替わりがあるのだ。体育館は、ビデオやデジカメを持ったたくさんの保護者が我が子に狙いを定めて撮影している。体育館は熱気で溢れていた。
(日記 孫の発表会を見るために、午前8時過ぎに息子宅を出て幼稚園へ向かった。初日の午前中に割り当てられているのだ。会場は熱気ムンムン。それでも、いい経験にはなった。午後は、孫たちのアルバム撮影と年賀状者写真撮影に写真館へ行くという。我々も付き合うことにした。7歳までの幼児のさまざまな衣装が並べてあるスタジオで孫たちは髪をセットし、いろんなポーズを決めながら、撮影するのだ。着飾った孫たちと一緒に、私たちも記念写真を撮った。楽しい経験だった。)