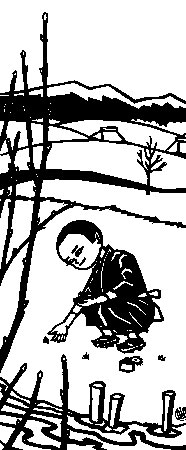自分の立場は?
自分の立場をはっきりさせず、相手を批判することは簡単である。どんな理屈でもどこかに弱点はあるもので、これを批判することは簡単である。
それをせず、単に批判しているだけでは片手落ちではないのか?そういう意味からすると、テレビに出てくるコメンテーターは、いいことを言っているが、「あなたならどうするの?」と問われたらどう答えるだろうか?
連日、普天間問題がテレビやラジオで取り上げられている。「俺んところへは絶対に来るな?」と叫んでいるところまでは、理解できる。しかし、日本の防衛を考えた場合に、どうするのがよいかを語ってはいない。
日本の防衛の問題を取り上げないで、基地をどうしたらよいかばかりを問題にしている。これでは、反対論しか出てこないのは当然である。
見つめたくない問題から目を背けて一部分だけを問題にしていても、解決は困難であろう。与党も野党も真剣に議論して、ベストでなくてもベターな方法を見いだしてほしいものだ。しかし、現実には、相手の批判ばかりしているように見える。
いいとこ取りはないのでは?
世の中、いいとこ取りはないのではないだろうか?我慢をせずに、いいところばかりを求めてもそうはうまくいくものではない。
私たちの若い頃に比べると、成人一人が車一台を所有する時代になってしまった。便利さを追うあまりに、誰もが車を手に入れることになったからだ。結果的に、地方のバスや電車は廃線の憂き目に遭うようになった。高齢者になったとき、きっと自分にしわ寄せが来るだろう。
原発は反対、電化製品は使いたい、冷暖房は欠かせないでは、どこか矛盾している。省エネだけだ解決するのだろうか?
子供が生まれたら、直ちに保育所や幼稚園に入れる。自分でみるという発想よりも、他人にみてもらうという発想の方が優先される。子育ての楽しさを味わうことも必要ではないのか?働き方を根本的に考える必要があるのではなかろうか?
一方自分の親も、同様である。身体が不自由になったら、直ちに施設へ預ける。そして、一生懸命働くのだ。車や電化製品などを買い求めるためには、働くしかないのだ。
しかし、自分が年老いたら、そのようなサイクルに入ることになるのだ。
「モノ」だけを追い求めても、幸せになれるのだろうか?「幸福度」を問題にしている国や自治体があるという。モノが少なくても、人と人とが心温まるつきあいをして生活する道があるのではないだろうか?
GDPよりGNHにという考えに賛成
先日テレビで、新しい言葉を耳にして感心しました。GDP(国内総生産)という言葉はよく聞きますが、最近、注目を集めているブータンの「GNH」という言葉です。GNHとは、Gross National Happinesuu(国民総幸福度)という意味です。
国の力や進歩を、「国民総生産」ではなく「国民総幸福度」で測ろうというこの「GNH」の考え方は、1976年の第5回非同盟諸国会議の折、。「GNHはGNPよりもより大切である」とブータンのワンチュク国王(当時21歳)が述べられたことに端を発しているそうです。
物質的な豊かさだけでなく、精神的な豊かさも同時に進歩させていくことが大事、との考えです。国王は、先進国を研究した結果、「経済発展は、対立や貧困問題、環境破壊、文化の喪失につながり、必ずしも幸せに放っていない。」という結論に達したそうです。
そこで、人々の幸せの増大を求めるGNHという考えを打ち出し、「開発はあくまで、国民を中心としておこなわれるべきである」として政治を行っているそうです。GNHは、ブータンの開発哲学であり、開発の最終目標になっているそうです。(インターネットも参照しました。)