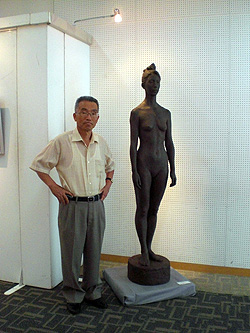情報の受信から発信へ
インターネット上のサーバに、不特定多数の利用者が投稿した動画を、不特定多数の利用者で共有し、視聴出来る動画共有サービスサービスがある。今から7年ほど前に登場したサービスで、日本でも急速に発展した。日本では数千万人、世界では数億人の利用者がいると言われている。
中でも、『YouTube』が人気あるようである。一般人が撮影して投稿したもの、自治体が作って投稿したもの、企業が作って投稿したものから、違法コンテンツまで様々なコンテンツが雑多に入り混じっている。
著作権上の問題が発生して新聞やテレビで問題になる場合もある。
私も、これらのこれらのコンテンツを利用することがある。これらの動画から学ぶことも多い。
しかし、こうした動画をただ見ているだけでは私は満足できない。情報の受け手になるだけではどうしようもない。時には、積極的に情報の発信者になってみたいと思っている。
以前にも書いたが、動画の情報発信者になるには、様々な機器やソフトが必要であり、技術も必要になる。時には、アニメーション制作能力も必要になってくる。
私は、今春の退職と同時に、デスクトップとノートのパソコンを購入した。そして、ソフトも最新のものを購入した。単体ではなく、セットで購入した。アドビ社のマスターコレクションシリーズCS4を買ったのだが、購入直後にバージョンアップしCS5が出た。
少しがかりしたが、以前のものはCS2だったので、「以前よりレベルアップしているので我慢するか」と自分を納得させた。ソフトは新しくなったが使いこなせないものが多い。
実は、昨日まで3日間受講したときに用いたホームページ制作ソフトの『Dreamweaver CS4』や画像編集ソフトの『Firewroks CS4』もセットの中に入っていたのだ。
画像編集をしようとすると一番先に困るのはファイル形式である。ちょうど昔ビデオの規格が異なっていたために、機器からテープ、録画機まで全部異なっていて互換性がなかったのだ。動画ファイルも同じようにいろいろあるのだ。これらの動画を編集しようとすると、ファイル形式が異なるために、画像編集ソフトでは読めなかったりして編集どころではない。
DVDを読み込むにしても、ファイル形式が異なると読み込めないので編集できない。そこで、今日の午前中、かつての同僚のSさんにお願いしてファイル変換について教えてもらった。また、コンピュータ会社へ行っているY君(息子の同級生)に早速「画像変換ソフト」を注文した(フリーソフトもあるのだが)。
ちょうどお腹が空いたときに、ご飯を炊くのならまだいいが、田植えをするように、いろいろ事前に勉強しておかなければならないことが多い。これからも、産業支援センターの『産業情報資料室』で書籍やDVDをお借りして、最低の基礎は理解しておきたいと思っている。
(日記:午前中、まず歯医者へ出かけ、事務所でSさんに動画ファイル変換について教えてもらう。午後は、日時を間違えて池田町まで行ってしまった。本当は日曜日であった。今後は日程をしっかり確認してから出かけなければならないと思った。夜、明日の施設の夏祭りの余興練習をする猪野瀬さわらび会の皆さんの練習を指導する。)