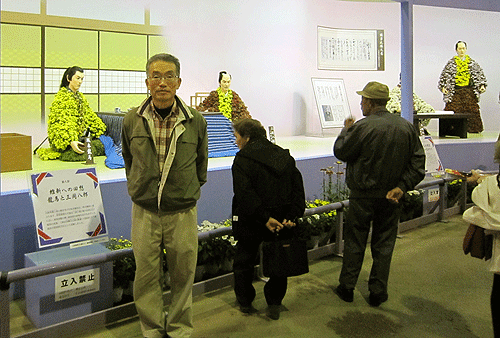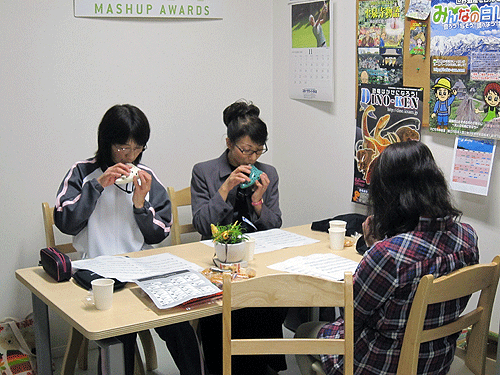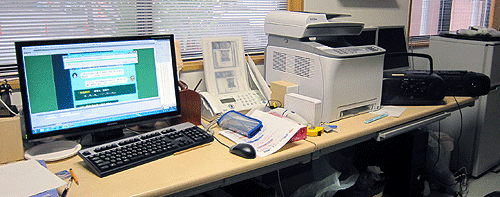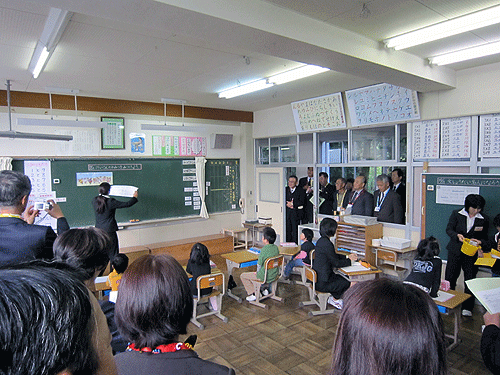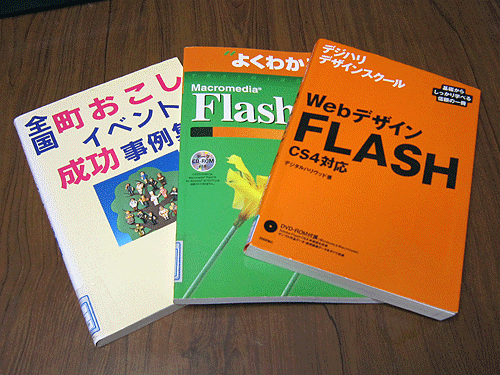武生菊人形で龍馬と出会う!
私は坂本龍馬が大好きだ。土佐藩の下級武士が、脱藩し、近代日本を開く原動力になったところがすばらしい。自分の国(土佐)では、殿様への目通りもかなわない下級武士でありながら、福井の松平春嶽公など当時の上層階級から下層階級まで様々な人たちと交流を深め、日本の危機を救った人物としてその人気は今も衰えていない。 特に、今年はNHK大河ドラマで『龍馬伝』が放映中であり、高知をはじめとする四国、九州でも、龍馬に関わるイベントが盛んに開催されている。私も、退職直後の4月に家内と九州、四国を車で回りながら、龍馬の足跡をたどったりもした。
また、恥ずかしながら、生まれて初めて歌謡浪曲に挑戦し、『幕末青春日記-龍馬』なる歌も作ったりした。これも、龍馬好きの私としては、是非ともやってみたいアクションの一つだった。
福井でいくつかの用事があったこともあって、思い切って「たけふ菊人形」も見に行くことにした。一番見たかったのは、OSK日本歌劇団のグランドレビューショウだ。
この中で、坂本龍馬のショウがあったからだ。主役の坂本龍馬を“桜花昇ぼるさんが演じていた。戦いの場面などもうまく表現されていた。
劇中に使われる音楽のボリュームはかなりのものであった。腹に響く重低音が終始会場に響き渡り、戦闘シーンの大砲などの音、殺陣のシーンでの剣と剣が打ち合った時の音など迫力満点であった。
ショウにおける音楽の使われ方が、興味深く、参考になる部分が多かった。特に低音部分の迫力は是非見習いたいと思う。
そして、いつの日にかミュージカル『平泉寺物語』を書いてみたいなあという漠然とした夢が再び頭の中に浮かんできた。しかし、これは簡単なことではないと思う。
その後、昼食の後、『菊人形館』を見学したが、龍馬の生涯が菊人形で表現されていた。特に、龍馬の活躍を支えた越前の人たちとの関わりを表す場面もあった。
今年の菊人形は龍馬が主役であった。 一年中、龍馬ブームが続いているようだ。私にとっては
来年以降が寂しくならないか心配である。 最後に、様々の種類の菊が咲き誇る会場を見て回った。同時開催されていた『北陸三県菊花コンクール』で勝山菊友会のT氏の「国華金山」が上位入賞していた。
天候に恵まれ、龍馬とも会えて充実した一日だった。平日のためゆったりと会場を見学することができた。入場者の多くは、高齢者であった。
(日記:『たけふ菊人形』を見に行く。その後、福井市内でいくつかの用事をした。また、楽器屋へ寄ってオカリナの本を2冊買った。)