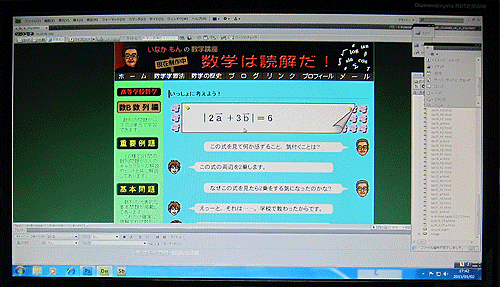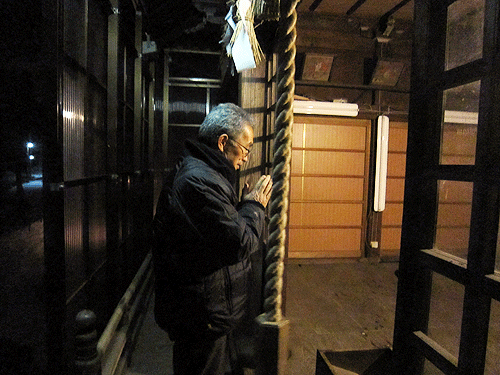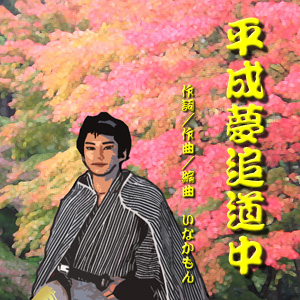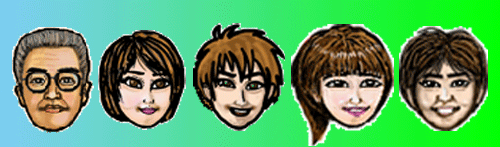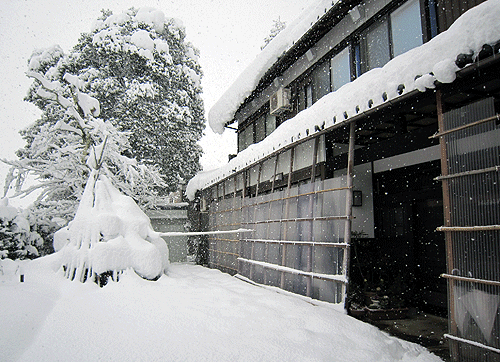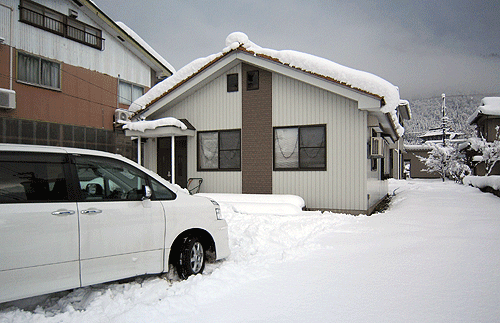久々のかき餅作り
私の代になっても、正月に鏡餅や雑煮などは作り続けたが、かき餅を作ることはなかった。食べるものが多くなり、かき餅への魅力がなくなっていたからだ。
思い起こせば、昔、かき餅は貴重なおやつだった。そのまま焼いても、油で揚げてもおいしかった。かき餅にもいろんな種類があった。海苔や海老の入ったもの、豆の入ったものなど様々な種類があった。
そして、薄く切ったかき餅は、藁で編んで部屋の天井などにつるしておいたのだ。子供の頃、遊んでいておなかが空いたときなどは、吊したかき餅めがけて下から衣服などを投げつけるとバラバラと落ちてきたものだ。
それらをポケットに入れて食べながら遊んだものだ。あの堅いかき餅を焼きもせず、揚げもせず、そのまま食べたのだ。かき餅の思いでは、空腹を抱えて遊んだ、幼い頃の思い出となって今も残っている。
今日、3日、かき餅を切ることにした。かき餅は二種類作った。海苔入りのものと海老入りのものを作った。薄緑とピンク入りのかき餅になった。薄く切るのにかなり時間がかかった。
それを、ひもで編んだ。昔は、わらで編んだが、今はその方法を覚えていない。そこで、娘の助けを借りて、細い麻紐で編んだ。編み終わるとそれらしくなった。
天井から吊すわけにもいかないので、使わなくなったぶら下がり健康器具に細い竹をくくりつけて、それに吊した。そして、寒い縁側に置くことにした。昔は、部屋の天井に吊ってあり、壮観なものだった。量も今と比べものにならない。
いつか、孫達と焼いて食べてみたいと思う。自分が食べたいというよりも、作る過程が楽しいことと、思い出がよみがえるからだ。昔は、家庭でいろんなことをやったものだとつくづく思う。一つ一つの行いが家族を結びつけていたように思う。
昔のことをすべて捨ててしまって、お金ですべてを解決する時代になったが、いっしょに大切な日本の心も捨ててしまっているような気がしてならない。昔に戻ることはできないが、昔の人たちが伝えて来た大切なものに思いを馳せることは忘れないでいたい。
(日記:箱根駅伝を聞きながら、かき餅作り。午後は、数学のホームページづくり。現役時代とは違って、休みの日が忙しく、平日の方が自由時間が多い。子供や孫達がやってきて我が家はとても賑やかだ。孫達を風呂に入れるのは私たち夫婦のつとめだ。今日で正月三が日も終わり。静かな年の初めであった。)