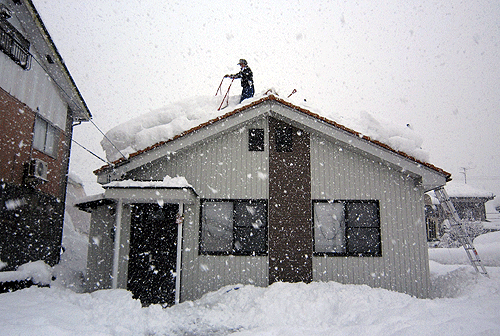里芋生産を続けるには
今日、午前9時半より、村の集会所で『片瀬の特産物(野菜、里芋など)を作ろう』研修会が開催された。講師は、福井県奥越農林総合事務所・農業経営支援部・技術経営支援課・産地育成グループ企画主査のDさんだった。
今日のテーマは主に、里芋についてであった。最初にJAのSさんが平成22年度の里芋生産についての報告があり、今後のJAの取り組みについての話があった。
その後、Dさんが「里芋生産の概況や問題点、今後の取り組み」などについて資料を使いながら説明があった。その後、質疑応答が行われ、活発な意見交換などが行われた。
奥越の里芋の生産高は、最盛期に比べると半減しているとのことであった。そして、作物による手間のかかり方などについての説明があった。
◇10aの手間と売上高◇
里芋 ………… 200時間 30~40万円
米 …………… 27時間 25万円
ネギ ………… 450時間 100万円
なす ………… 500から600時間 150万円
私の集落片瀬は、後継者不足のため会社方式で農業をやっている。「農事法人かたせ」という組織を作って米作りなどを行っている。ここで、採算が合うのは、米だけということだ。
かつて、米はとても手間のかかる作物だった。米という字が「八十八」と書くように、とても作業工程の多い作物だったということだ。そして、作業の多くに、女性が関わってきたのだ。腰を曲げての作業が続く過酷なものだった。
しかし、土地改良が行われ、機械化が行われた結果、米作りのほとんどは、男性の仕事になった。現在、米作りは」私の子供時代と比べるとずいぶん変わってしまった。
先ず苗作りはほとんどJAに委託し、コンバインで収穫したら、田んぼからJAのカントりーへ一直線に籾を運ぶのだ。そして、乾燥から臼すりまでを委託するのだ。
また、田植え機で苗を植えると同時に、肥料と除草剤までまいてしまうのだ。昔は大変だった草取りは除草剤を使用、化学肥料や農薬によってかなりの手間を省くのだ。
そして、最も手間のかかる作物だった稲作は、労働時間を大幅に短縮したのだ。同じような方法で米を作っている外国では、日本の何分の一かで米作りを行っているのだ。
米作りと言っても、ある部分だけを請け負っているように見えなくもない。1から10までこなしてきた昔の米作りに比べるとかなりの省エネだ。
このような米の作り方がよいのか悪いのかは別として、里芋もゆくゆくはこのような方式に移るだろう。寒風吹きすさぶ11月中旬前後の里芋の収穫作業は高齢者には過酷だ。この部分の機械化は、どんどん普及するだろう。
個人の楽しみと、集団での機械化を組み合わせた里芋生産ができないのだろうか。私は、どこかに道はあると信じている。今こそ、知恵を出すときだ。
規模の大小は別として、農家自らが経営者(少し大げさか)だった農業は今大きく形を変えようとしている。人と人との交わりが多かった(結いなどを通して)農業は形を変えていくだろう。
それは、集落の崩壊にもつながる方向に向かっているようにも思われる。農業は、採算面ばかりではなく、高齢者の生き甲斐にもつながり、まちづくりにも多いに寄与していたはずだが、今、その形を変えようとしている。
私には、何か策があるように思えてならない。今年は、微々たる一歩でも進めたらと思っている。
(日記:午前中、『片瀬の特産物(野菜、里芋など)を作ろう』研修会に出席。質問もする。午後は、事務所で数学のホームページ作り。時々、運動を兼ねて事務所の駐車場の排雪。)