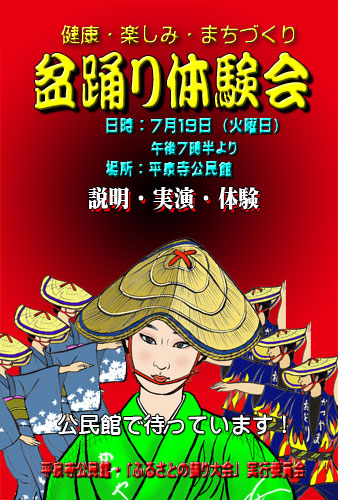デスクワークとは違う充実感
来週の火曜日に両手の指(腱鞘炎)を手術するので、“今のうちに身体を使う仕事をやっておかなければ”と朝から忙しい。
先ず朝一番に、田んぼの畦の草刈りだ。田んぼは法人に預けてはあるが、今年から畦の草刈りは自分ですると決めた。作年までは、水管理も草刈りも全て法人に丸投げだった。
今年は、草刈りだけは自分ですることにした。もちろん会社組織なので、その分、手当は出るのだが。今日は、紐ではなく、回転刃で草刈りを行った。
回転刃は、草はよく切れるが、石に当たるとキーンといやな音がするのと刃が痛むのが難点だ。また、用水のコンクリート枠の際もうまく切れない。
畦の草刈りは、土手があって平地ではないので、足腰に負担がかかる。汗だくになった。毎日2回はシャワーをしなければならない。体重はどんどん減って、標準体重になった。
ピーク時と比べると、約20kg痩せたことになる。これ以上痩せると健康にもよくないのではと心配になった。とにかく汗のかく量は半端ではない。デスクワークとは全く異なる充実感がある。昔の人はよく言ったものだ。「晴耕雨読」と。
午後は、開墾をすることにした。田んぼの畦際にかなりのスペースがあって、ただ雑草が生えているだけの所があった。ここを開墾して、作物や花を植えない手はない。

全て買ったトマト苗の脇芽で育てたトマト苗。全ての鉢の底から、白い根が顔を出している。
自宅には、買ったトマトの苗の脇芽で育てたとトマト達が出番を待っているのだ。鉢植えで育てようと思ったが、トマトの根は勢いよく下へ伸びて、全ての苗の根が鉢の底から白い根を出しているのだ。
鉢で育てるのは無理だ。そこで、この開墾した畑にトマトを植えることに決めた。開墾した場所には、雑草が生えていたので、草の根がいっぱいあり、石もたくさん出てきた。
トマトにとっては条件はよくないだろう。今日は畑を耕し、堆肥を入れ、石灰をまいておいた。2、3日このままにしておいて、マルチを掛け、家のトマト達を植えたいと思う。果たしておいしい実をつけるだろうか。
6時過ぎまで、開墾作業をした。予想通り、近くの人が「何してるん?」と、近寄ってきて、立ち話をすることになった。今は余裕を持って立ち話をすることができる。
肉体労働で、身体は疲れたが、気分は爽快だ。思いっきり、働いて汗を流せば、無理にダイエットをしなくても、自然に痩せることができる。気持ちのいい一日だった。
(日記:午前中、田んぼの畦の草刈り。午後も、草刈り。その後、開墾作業。家内はニンニクの保存作業とニンニクの醤油漬けを作っている。夜は、ニンニクを油で揚げた。とてもおいしい。家内も喜んで食べた。思いっきり汗をかいたのでビールがうまい。夜は、明日の「おじさんバンド」の練習に合わせて編曲作業。 )