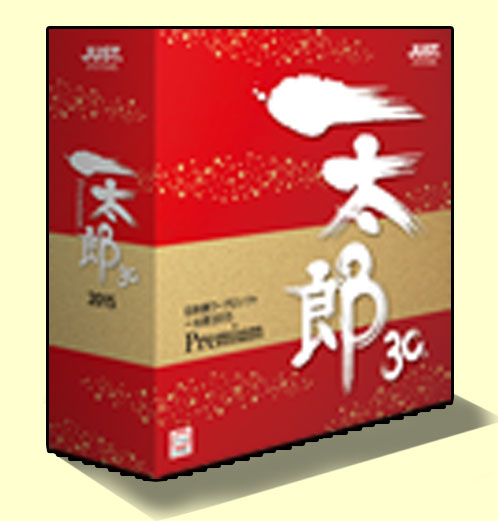漫画『三丁目の夕日』から
二ヶ月に一度の定期検診のついでに眼科へ寄った。診察室の真ん前にある書棚にはたくさんの漫画の本が置いてある。そこに、たくさんの『三丁目の夕日』があった。
単行本は、読み切りの集まりになっている。その中に一つに10ページ前後の「すきやき」と題したまん画があった。少しリッチな友達の家で“すき焼き”をご馳走になった主人公が、家へ帰って家族に「我が家でも“すき焼き”をしてほしい」と毎日おねだりする漫画だ。
しかし、あまり豊かでない生活を送っている主人公の家ではなかなか“すき焼き”をする余裕がない。両親は子どもの望み通りに“すき焼き”をしてやりたいのだが、家計が許さない。
そして、ずいぶん月日が経過したある日、“すき焼き”が実現するのだ。しかし、その“すき焼き”は、肉が少なく野菜の多いものだった。肉は、友達の家でご馳走になったような牛肉ではなく、豚肉だ。それでも、家族はうまいうまいと言いながら食べるというところで終わっている。
さて,子どもの頃の我が家だが、“すき焼き”を食べる日はまるで祝日のように決まっていたものだ。臼擦りが終わった日(米作りの最終日)と大晦日の2回だ。肉は上等なものではなかった。大晦日に“すき焼き”を食べる習慣は今でも続けている。今はいつでも食べられないことはないが、カロリーの面から普段は敬遠している。時代は変わったものだ。
(日記 自宅を9時半に出発。二ヶ月に一度の定期検診。ついでに眼科でも診てもらうことにした。ドライアイで涙が出るので困っている。その後、芦原温泉へ。ここしばらくの種々の行事の打ち上げのつもりで出かけた。温泉につかり、家内とカラオケを存分に楽しんだ。)