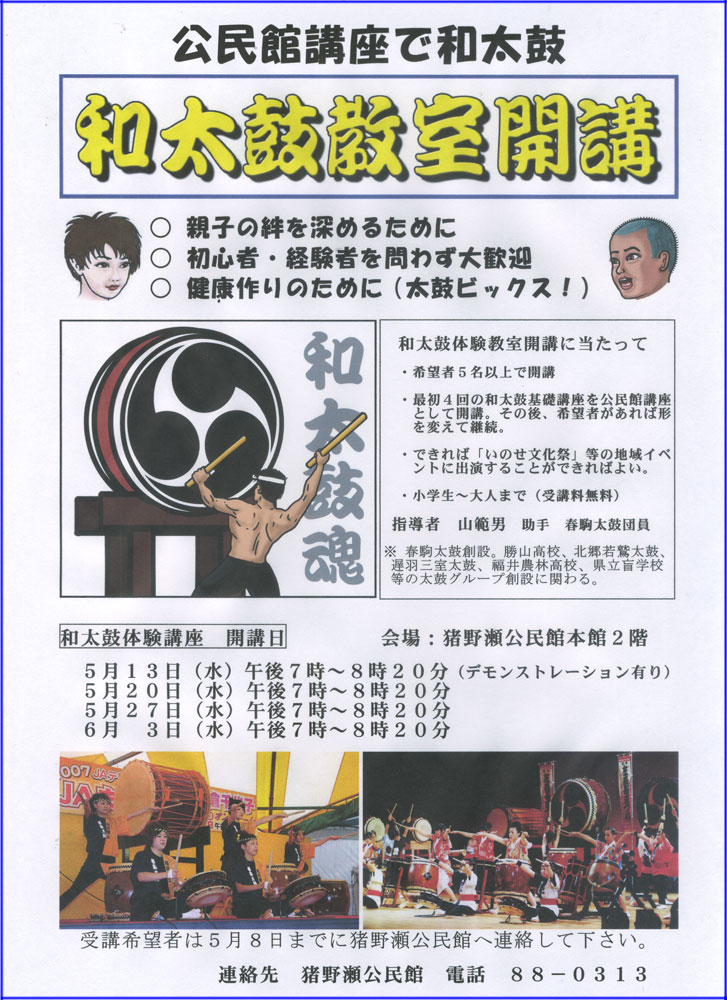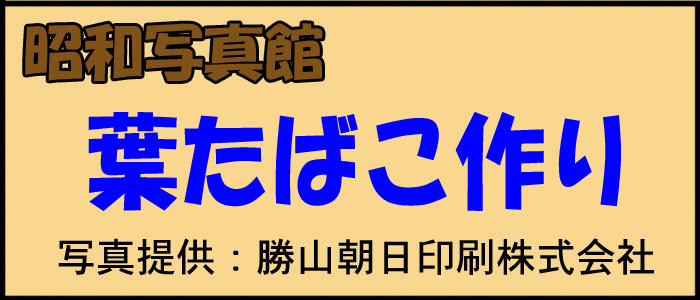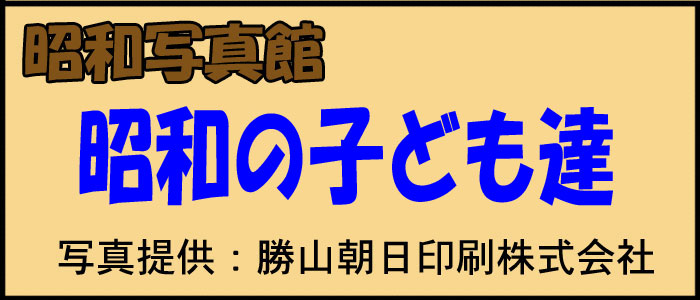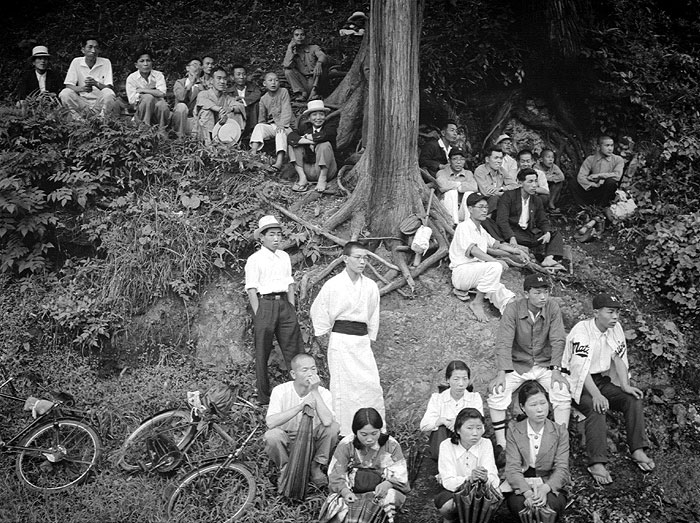これで新しい楽器は最後にしたい
私は、楽器に関しては移り気かもしれない。思い出してみると中途半端な楽器が多い。ハーモニカに始まり、ギター(エレキ・クラシック・フォークなど各種)、ドラム、ハワイアンギター、ウクレレ、オカリナ、三味線(民謡・津軽三味線)、半音階の出るクロマチックハーモニカ、和太鼓、篠笛、……。どの楽器も自分を十分楽しませてくれたから後悔はしないが。

ウインドシンセ「EWI5000」
そして、最近、新しい楽器を買った。と言うよりも、これまで持っていた楽器の上位機種を買ったのだが。シンセサイザーの「笛バージョン」というところか。形としては、クラリネットに似ている。
サックスやクラリネットを吹きたいがこの年では無理だろうと思って、代替楽器としてこのウインドシンセサイザーを買ったのだ。楽器のボタンを切り替えることによって、いろんな楽器の音が出るのだ。
実は、最初は、この楽器の普及版「EWIUSB」を買って練習したのだ。楽器としては気に入っている。ギターのOさんと月に数回わがスタジオでアンサンブルを楽しんできた。
そして、去年の暮れ、公民館ではボーカルのYさんと組んで人前で演奏することができた。しかし、この「EWIUSB」の電子的な部分はパソコンによって動かしているので、どうしてもパソコンが必要だった。そのために、小型のパソコンも買ったのだが面倒だ。

ハワイアンバンドでフラダンス
しかし、新しい楽器は、すべてが楽器本体に内蔵しているのでスピーカーさえあれば音を出すことができるのだ。一人で練習するなら、ヘッドフォーンかイヤホンがあればどこでもできるのでありがたい。
やってみたい曲を決め、CDなどを聞いてまず最初に練習用カラオケを作るのだ。そして、バンド用に編曲し、それぞれが自主練習して合わせるというパターンだ。施設慰問や地域のイベントで演奏してみたいと思う。
(メモ 数学参考書作り。ウオーキング。数学の模擬試験問題を解く。)

 よりも充実した生活を送り、諸問題を見事に解決していったのである。私には、理想の退職生活のようにも思える。
よりも充実した生活を送り、諸問題を見事に解決していったのである。私には、理想の退職生活のようにも思える。