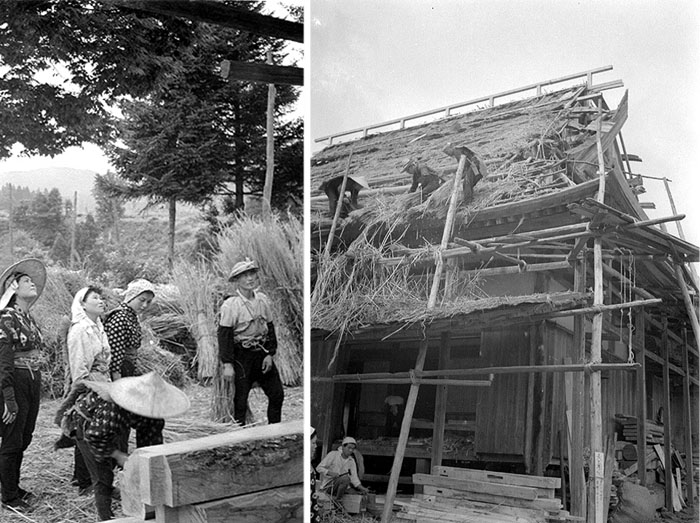不良品などトラブルがあったときには
市内や県内で買えるものはなるべく買うようにしているが、専門的なものとなると、市内県内では注文のしようがない場合が多い。
ネットで注文した場合に、何か問題があったときにはどうしたらよいのか?この部分が田舎に住むものにとって最大の懸念材料であった。
今日あったことも含めて、具体的な例を三つあげてみたい。
その1……ある業者を通してキーボードとヘッドフォンマイクを購入した。注文する前に調べてあるので、楽器はどこの製品かがよくわかる。しかし、小物のマイクとなると調べずに買った。
ところが、マイクの方がうまく作動しない。そこでメールでその旨を伝えると、早速宅急便で新品が送られてきた。そして、元の不良品を送り返す箱まで送られてきた。住所も書いてあるので、宅急便の業者に渡すだけだった。
手間もほとんどかけず、一本のメールで新品と交換してもらえた。こちらの方は今も、順調に作動している。ちょっとネットを見直した。
その2……昨日のこと、最新式のウインドシンセサイザーが急に作動しなくなった。これも福井の楽器点でも売っていないものなので、昨年暮れにネットで注文した。注文先は東京の某カメラ店。
電子楽器の怖いところは、トラブルがあっても素人にはどうしようもないということだ。楽器店の店員さんも対応できないようだ。症状を伝えると、修理の方法は二つあるという。一つそのカメラ店へ楽器を持ち込めば、メーカーに渡して修理してくれるという。保証期間なので、こちらのミスでの破損でなければ無料だという。
しかし、まさか東京まで楽器を運ぶわけにも行かない。次の方法は、送料はかかるが、引き取りサービスがあるという。宅急便の業者が取りに来てくれて、メーカーで修理し、それをまた自宅へ届けてくれるという。3,000円くらいの送料はかかるがやむを得ない。
修理する方法はあるとわかったので、今度は購入先ではなく、楽器を扱う会社のカスタマーサポート部へ電話をかけた。技術者が対応してくれた。症状を聞いて、対処法を教えてもらった。5分で直ってしまった。あれほどスイッチも効かず、ディスプレイに文字が出たままで手の施しようがなかったのに。
その3……最近、それまで使い続けている音楽ソフトの5代目ぐらいにあたる最新のものに更新した。バージョンアップしながらここ2,30年は使い続けているソフトだ。歌を作るのもCDにするのも、歌や楽器の練習をするためのカラオケを作るのにも使える愛用のソフトだ。
しかし、マニュアルが高等すぎて私の手に負えない部分が多々ある。そこで、その旨をメールすると、毎回即座に丁寧な回答があるのだ。しかも、手順を示すパソコン画面の絵まで添付してあるのだ。
しばらく、メールの交換が続いた後、「一度電話で話しましょう」とまで言ってくださった。パソコンを見ながら、対応することができた。
上記のような例から、最近、通販が広がる理由を見たような気がした。要は、アフターサービスだ。新製品が出てきて品物が高度化・電子化すると、地方の販売店では対応できないのだろう。販売すらできないものが多くなってきた。それらに対応する技術者がネットで答えてくれるシステムだ。ネット販売はまだまだ普及しそうな勢いである。